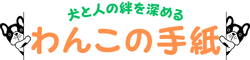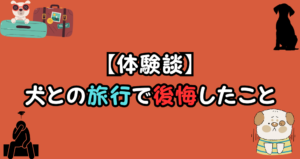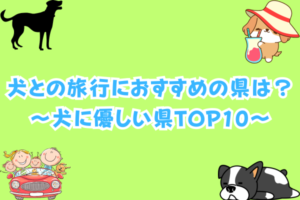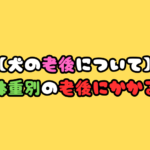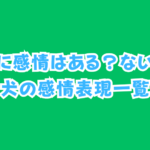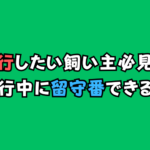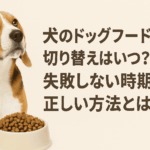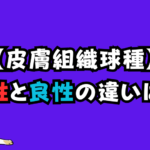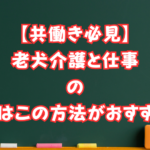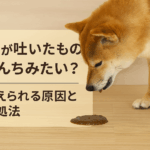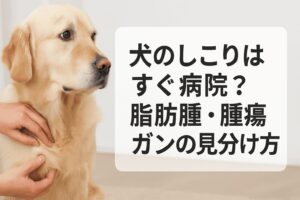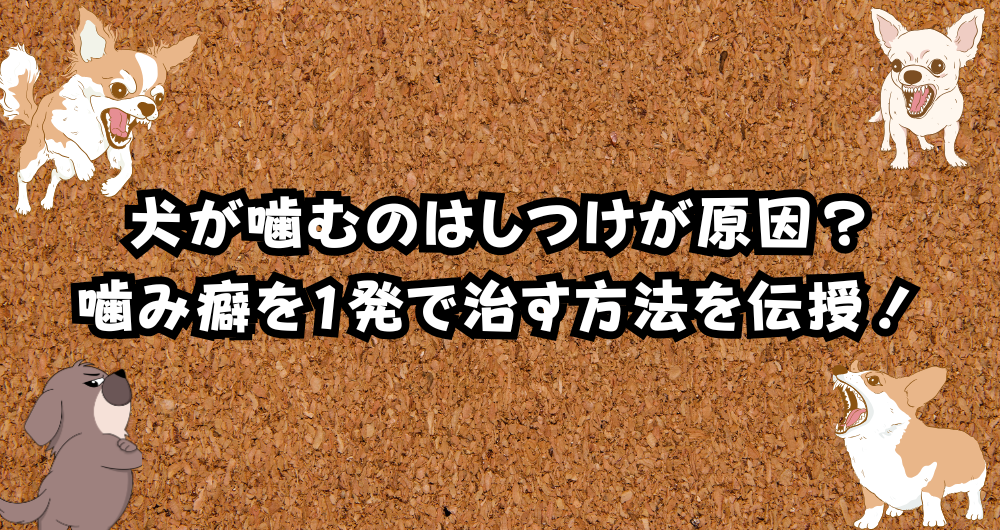
「愛犬の噛み癖が治らなくて困っている」そんな悩みを抱える飼い主さんは少なくありません。
犬が噛む行動は、時には愛らしい仕草として受け取られることもありますが、状況によっては他人や他のペットに迷惑をかけたり、飼い主自身がケガをしてしまったりすることも。
特に、成犬になってからの噛み癖は深刻な問題となり得ます。
このページでは、犬が噛む原因を解明し、噛み癖を一発で改善するための具体的な方法を伝授します。しつけのポイントや失敗例も併せて紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
なぜ犬は噛むのか?噛み癖の原因を解説
犬が噛むのにはさまざまな理由があります。
主に以下の3つに分類されます。
- ストレスや不安
- 遊びの一環
- 本能的な行動
それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。
(1) ストレスや不安
犬は環境の変化や孤独感を感じると、不安を噛む行動で表現することがあります。
たとえば、飼い主が仕事で長時間不在にする場合や、新しい家族が加わった場合などが原因となることが多いです。
(2) 遊びの一環
特に子犬は、遊びの一環として噛む行動を見せることがあります。
これは成長過程での自然な行動ですが、適切なしつけを行わないと成犬になってからも続いてしまいます。
(3) 本能的な行動
犬は縄張り意識や防衛本能から噛むこともあります。
特定の状況で自分や家族を守るための行動ですが、この場合もしつけが不十分だと、他人や他の犬に攻撃的な行動を取るようになる可能性があります。
これらの原因を理解することで、適切な対応が可能になります。
噛み癖を放置するとどうなる?
噛み癖を放置することには大きなリスクがあります。
以下にその例を挙げます。
- 噛み癖がエスカレートする
- 他人や他の犬への迷惑
- 飼い主との信頼関係が損なわれる
それそれを詳しく見ていきましょう。
(1) 噛み癖がエスカレートする
放置された噛み癖は、エスカレートしてしまうことがあります。
最初は軽く遊びで噛んでいた行動が、次第に力強い噛みに変わり、最悪の場合、人や他の犬に深刻なケガを負わせる原因となります。
(2) 他人や他の犬への迷惑
散歩中やドッグランで他の犬や飼い主に噛みつく行動を取ると、信頼を失うだけでなく、法律的な問題に発展する可能性もあります。
(3) 飼い主との信頼関係が損なわれる
噛み癖が改善されないことで、飼い主が犬に対してストレスを感じるようになり、結果的に信頼関係が損なわれることがあります。
噛み癖を改善するための基本ステップ

一度噛み癖がついてしまった犬は、もう改善できないと思っている人は多いですが、そんなことはありません。
どんな犬でも、子犬でも成犬でも老犬でも必ず噛み癖は治ります。
「愛犬の噛み癖が治らなくて困っている...。」という方は、以下の方法を実践してみてください。
①基本的なしつけの徹底
②噛む行動を抑制する環境づくり
③コマンドで改善を目指す
それでは、詳しく見ていきましょう!
①基本的なしつけの徹底
まずは飼い主の態度が重要です。
毅然とした態度を保ちながらも、犬に対して愛情を持って接することが必要です。ポジティブ・トレーニングを取り入れることで、犬が学びやすい環境を作りましょう。
また、信頼関係の構築のために、「おすわり」や「待て」など基本的なしつけを徹底し、主従関係をはっきりさせるも重要です。
しつけの際は、罰を与えるのではなく、正しい行動を取った際に褒めることで犬も理解してくれるようになります。
②噛む行動を抑制する環境づくり
犬が噛んでも良いおもちゃを与えることは非常に効果的です。
また、ストレスを感じさせない生活リズムを構築することも重要。たとえば、適度な運動や食事の管理が役立ちます。
③コマンドで改善を目指す
具体的なコマンドトレーニングを実践しましょう。
たとえば、噛む行動が見られた際に「ストップ」というコマンドを使い、アイコンタクトを取りながら犬を落ち着かせます。
この方法は、一貫して行うことが重要です。
よくある失敗例とその対策
犬の噛み癖を治そうとしても、「失敗した。。。」、「全然噛み癖が治らない。。。」なんてことも多々あります。
なぜ、噛み癖が治らないのかというと、根本的にしつけ方法が間違っているからです。
あなたの愛犬の噛み癖が治らない場合は、以下のような行動を取っていないか思い出してみてください。
- 怒りすぎて犬が怯えてしまう
- 噛むたびに過剰に反応する
それでは、具体的に詳しく説明していきます。
(1) 怒りすぎて犬が怯えてしまう
噛み癖に対して怒りすぎると、犬が飼い主を怖がり、信頼関係が損なわれる可能性があります。
適切なトーンで指示を出しましょう。
(2) 噛むたびに過剰に反応する
噛む行動に過剰に反応することで、逆に犬がその行動をエスカレートさせる場合があります。
冷静に対応することが大切です。
【体験談】噛み癖改善の成功例
実際に噛み癖改善に成功した飼い主のエピソードを紹介します。
最初は遊んでいるつもりでも噛むことが多かったのですが、しつけをしっかりと始めたことで、犬自身が噛んではいけないと意識し始めました。特に、「噛まないで」という指示を出し、噛んだらすぐに無視することで、少しずつ噛む回数が減っていきました。
噛み癖を直すために、おもちゃを与えることに集中しました。最初は自分の手や服を噛んでいたけれど、おもちゃで代替えをすることで、徐々に噛む対象が変わり、噛む回数が少なくなったように感じます。おもちゃの種類もいろいろ試してみましたが、特に硬めのものが気に入ったようです。
犬が噛んだ瞬間に、しっかりと「ダメ!」と叱ることが効果的でした。最初はなかなか理解してくれなかったけれど、噛む行為をしたらすぐに反応し、その後は噛むことを避けるようになりました。タイミングが大事だと実感しました。
他の犬や人との交流を増やすことで、噛み癖が減ったように感じました。社会化を進めることで、犬は自分の立ち位置や相手との距離感を学び、無駄な噛みつきが減少しました。特にドッグランに行ったり、犬同士で遊ばせたりすることが効果的でした。
噛まなかったときにはすぐにおやつを与えるようにしました。ポジティブな強化をすることで、「噛まない方がいい」と犬が学んでいったように思います。最初はうまくいかないこともありましたが、忍耐強く続けることで、噛まなくなる時間が長くなり、最終的に噛み癖が改善されました。
【まとめ】しつけ次第で噛み癖は改善できる
噛み癖のある犬のしつけ方、実際に噛み癖が治った体験談を紹介してきましたが、いかがでしたか?
噛み癖はしつけ次第で必ず改善できます。飼い主の一貫した努力と、犬に対する正しい接し方がとても大切だということが分かっていただけたら幸いです。
犬を飼うということは、家族になるということ。一緒に暮らしていれば、お互いが理解できないことはありますし、ストレスが溜まることもあるでしょう。
しかし、それは人間だけではなく、犬も感じています。だからこそ、お互いの事を理解し、しっかりと絆を深めていけるように愛情を持ってしつけをしていきましょう。
そうすることで、自然とワンちゃんも理解してくれるようになり、気付いたら噛み癖は治っているはずです!