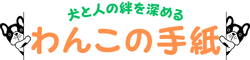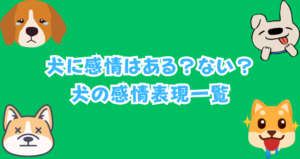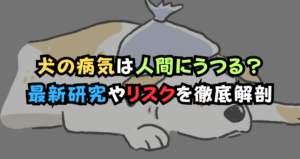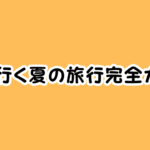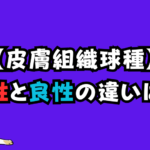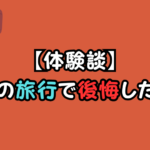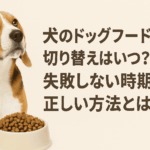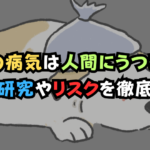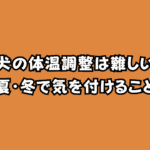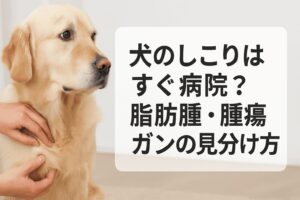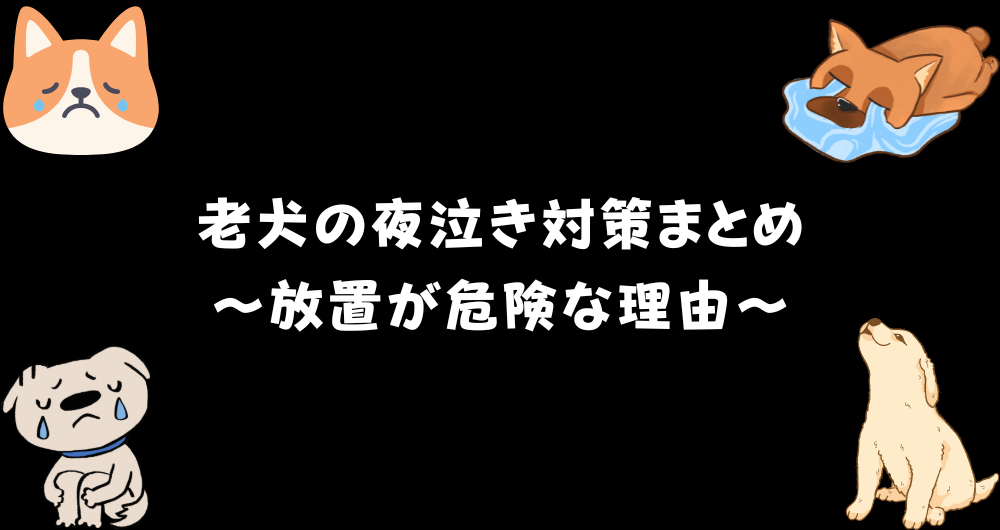
成犬のうちは大丈夫でも、老犬になると夜泣きが多くなります。
もちろん、夜泣きしないワンちゃんもいますが、夜泣きで悩む飼い主が多いのも事実です。
実際に老犬の夜泣きが始まると、「原因は何?」、「対策方法は?」、「放置しても大丈夫?」などと疑問が多く出てきます。
そこでこのページでは、老犬の夜泣きの原因や対策、放置しても問題ないのかについてを解説していきます。
老犬の夜泣きとは?放置が危険な理由
老犬の夜泣きとは、夜中に突然吠えたり遠吠えをする行動のことを指します。
原因はさまざまですが、主に加齢による変化が影響しています。老犬になると視力や聴力の低下が進み、環境の変化に敏感になります。
さらに、昼夜のリズムが崩れたり、不安を感じやすくなったりすることで夜泣きが起こるのです。
老犬の夜泣きを放置するリスク
老犬の夜泣きを放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 認知症の進行:脳の老化が進み、症状が悪化する可能性があります。
- 睡眠不足による健康リスク:睡眠の質が低下し、体調不良や免疫力低下につながることがあります。
- 飼い主の負担増加:夜間の吠えにより、飼い主の生活にも影響を及ぼします。
- 近隣トラブル:マンションや集合住宅の場合、騒音トラブルの原因になることも。
愛犬の夜泣きを軽視せず、早めに対策を講じることが大切です。
まずは夜泣きの原因を理解し、適切な対応を考えましょう。
老犬が夜泣きをする主な原因

老犬の夜泣きの原因はさまざまですが、大きく分けて以下のような要因が考えられます。
- 認知症(認知機能不全症候群)
- 不安や寂しさ
- 体の痛みや不調
- 生活リズムの乱れ
それでは、具体的に1つずつ見ていきましょう。
①認知症(認知機能不全症候群)
犬も人間と同様に、高齢になると認知症を発症することがあります。
認知症になると、昼夜の区別がつかなくなったり、不安感が増したりすることで夜泣きが発生することがあります。
認知症になると、以下のような行動が見られます。
- 夜中に意味もなく歩き回る
- 同じ場所をぐるぐる回る
- 急に大声で吠え出す
- 昼夜逆転の生活リズムになる
認知症の進行を遅らせるためには、適度な運動や脳を刺激する遊びを取り入れることが有効です。
② 不安や寂しさ
老犬は視力や聴力が低下するため、周囲の環境を正しく把握できなくなり、不安を感じやすくなります。
特に、飼い主の姿が見えないと不安を感じて夜泣きすることがあります。
不安や寂しさを紛らわすには、以下の方法が有効です。
- 飼い主の匂いがついた布や毛布を用意する
- そばに寝床を配置し、安心感を与える
- 夜間でも声をかけることで安心させる
③体の痛みや不調
老犬は関節炎や内臓疾患など、加齢に伴う健康問題を抱えていることが多いです。
痛みが強いと眠れずに鳴くことがあります。
加齢に伴う不調には、以下のようなことが多いです。
- 関節炎による痛みで寝返りが打てない
- 消化不良や胃腸の不調による不快感
- 尿意や便意による頻繁な目覚め
痛みが原因の場合は、獣医師と相談し、適切なケアを行うことが重要です。
④生活リズムの乱れ
老犬は日中に運動量が不足すると、夜になっても眠くならずに活動的になってしまうことがあります。
生活リズムの乱れの原因は、以下の通り。
- 日中の刺激が少なく、エネルギーが余っている
- 夕方以降に昼寝をしすぎている
- 飼い主の帰宅時間に興奮し、その後落ち着かない
この場合は、日中の活動を増やし、適度な刺激を与えることが改善のポイントになります。
老犬の夜泣き対策!今日からできる改善方法
老犬の夜泣きを改善するためには、生活習慣の見直しと環境の調整が重要です。
ここでは、今日から実践できる具体的な改善方法を紹介します。
① 生活リズムを整える
老犬の夜泣きの原因の一つに、生活リズムの乱れがあります。
昼間に活動量が少ないと、夜になっても眠れずに吠えてしまうことがあります。
改善方法は以下の通り。
- 朝夕の散歩を欠かさない:短時間でも良いので、毎日決まった時間に散歩をすることで生活リズムを整える。
- 食事の時間を一定にする:朝・夕にしっかりと食事を与え、夜間に空腹で目覚めるのを防ぐ。
- 昼間の刺激を増やす:知育玩具を活用して、日中に脳を使う遊びを取り入れる。
②夜間に安心できる環境を整える
老犬は暗闇を怖がることがあり、不安から夜泣きにつながることがあります。
安心して眠れる環境を作れるように、以下の方法を試してみてください。
- 寝床の位置を見直す:飼い主のそばに寝床を置くことで安心感を与える。
- ナイトライトを活用する:真っ暗な状態を避け、薄暗い明かりをつけることで安心感を提供。
- 温度管理を徹底する:寒すぎたり暑すぎたりしないように、エアコンやヒーターを活用。
③リラックスできる時間を作る
夜寝る前にリラックスできる時間を作ることで、老犬の夜泣きを軽減できることがあります。
以下の方法がおすすめです。
- 優しくマッサージをする:体をほぐすことでリラックスし、安心感を与える。
- 静かな音楽を流す:クラシック音楽やホワイトノイズを活用すると、リラックス効果が期待できる。
- 寝る前に軽い散歩をする:軽く体を動かすことで、適度に疲れさせて眠りやすくする。
④ 健康状態をチェックする
老犬の夜泣きは、体の不調が原因で起こることもあります。
以下のことを重点的に日頃からチェックしましょう。
- 関節痛や歯の痛みがないか確認する
- トイレの失敗が増えていないかチェックする
- 夜間に頻繁に起きて水を飲む場合は腎臓の病気を疑う
もし健康上の問題が疑われる場合は、獣医師の診察を受けるようにしてください。
夜泣きを防ぐための環境づくり

老犬の夜泣きを防ぐためには、安心して眠れる環境を整えることが重要です。
環境が変わることで不安を感じる犬も多いため、飼い主が意識して快適な睡眠環境を提供する必要があります。
ここでは、老犬が安眠できる環境づくりに関してを紹介していきます。
①静かで安心できる寝床を用意する
犬は環境の変化に敏感です。
夜泣きを減らすためには、静かでリラックスできる寝床を作ることが重要です。
- 寝床の場所を見直す:騒音が少なく、落ち着ける場所に寝床を配置する。
- クッション性のあるベッドを用意する:老犬の関節に優しい低反発マットやクッションを活用。
- 飼い主の匂いがついた毛布を使う:安心感を与えることで、ストレスを軽減。
②温度や湿度を適切に調整する
老犬は体温調節が苦手なため、快適な温度・湿度を保つことが大切です。
- 冬場は暖房や毛布を活用:寒すぎると関節がこわばり、痛みの原因になる。
- 夏場はクールマットやエアコンを活用:暑すぎると眠れず、夜泣きの原因になる。
- 湿度を50~60%に保つ:乾燥や蒸し暑さを防ぎ、快適な睡眠環境を作る。
③明るさを調整し、安心できる空間を作る
老犬は視力が低下してくると、暗闇を怖がることがあります。
そのため、適度な照明を用意すると安心して眠ることができます。
- ナイトライトを設置する:完全な暗闇にせず、ほんのり明るい環境を作る。
- 日中は自然光を取り入れる:体内時計を整え、昼夜のリズムを維持する。
④ 外部の刺激を減らす
老犬は外の物音や光が原因で夜泣きが起こることもあります。
そのため、不要な刺激を減らす工夫が必要です。
- カーテンを厚手のものにする:外の光や音を遮断し、落ち着ける環境を作る。
- 防音マットを活用する:外部の騒音を軽減し、快適な睡眠環境を提供。
⑤飼い主がそばにいると感じさせる
老犬は不安を感じやすいため、飼い主の存在を感じられる環境を作ることで安心して眠れるようになります。
- 飼い主の匂いがついた布を寝床に置く
- 寝室の近くに寝床を設置する
- 眠る前に優しく声をかける
これらの工夫を取り入れることで、老犬が安心して夜を過ごせる環境を整えることができます。
夜泣きがひどい場合に試すべきサポート方法
夜泣きがなかなか改善しない場合は、さらなるサポート方法を検討する必要があります。
ここでは、夜泣きがひどいときに試してみるべき具体的な対策を紹介します。
①獣医師に相談する
夜泣きの原因が体調不良や病気によるものかもしれません。
特に、以下のような症状が見られる場合は、すぐに獣医に相談しましょう。
- 夜間に頻繁に吠えたり鳴いたりするが、日中は比較的落ち着いている
- 体を頻繁に掻いたり舐めたりする(皮膚炎の可能性)
- 目が見えづらくなっている、壁にぶつかる(視力低下の可能性)
- 関節が硬くなり、歩きにくそうにしている(関節炎やヘルニアの可能性)
獣医師に相談することで、夜泣きの原因が病気や痛みである場合に適切な治療を受けることができます。
②フェロモン製品を活用する
犬がリラックスしやすい環境を作るために、フェロモン製品の使用も有効です。
- フェロモンディフューザー:コンセントに差し込むだけで、犬を安心させるフェロモンが拡散される。
- フェロモンスプレー:寝床やクッションにスプレーすると、リラックス効果が期待できる。
- アロマテラピー:ラベンダーやカモミールの香りは犬にもリラックス効果があるとされている。
③ サプリメントや安定剤を試す
睡眠を促す成分を含むサプリメントや、獣医師が処方する安定剤を活用することで、夜泣きを軽減できることがあります。
- メラトニンサプリメント:犬の睡眠リズムを整える効果がある。
- カモミールエキス:リラックス効果があり、穏やかな睡眠を促す。
- 獣医師処方の安定剤:ストレスや認知症による夜泣きがひどい場合に処方されることがある。
④ 介護用おむつやトイレ環境を見直す
夜泣きの原因が排泄に関連していることもあります。
高齢になるとトイレの間隔が短くなり、夜中に排泄のために鳴くことがあります。原因が排泄である場合は、以下の事を実践してみてください。
- 寝る前に必ずトイレに連れて行く
- ペット用のおむつを活用する
- 室内トイレの設置場所を見直す(移動が困難になっている場合、寝床の近くに配置)
⑤夜間の見守りカメラを活用する
ペットカメラを設置することで、夜間に犬がどのような行動をしているかを把握することができます。
- 夜中に吠える前の行動をチェックする:興奮状態なのか、不安なのかを見極める。
- リモートで声をかけられる機能を活用する:遠隔操作で飼い主の声を聞かせると、犬が安心することもある。
これらの方法を試すことで、老犬の夜泣きが少しでも改善される可能性があります。
重要なのは、犬の状態をよく観察し、最適な対策を講じることです。
老犬の夜泣きを悪化させるNG行動
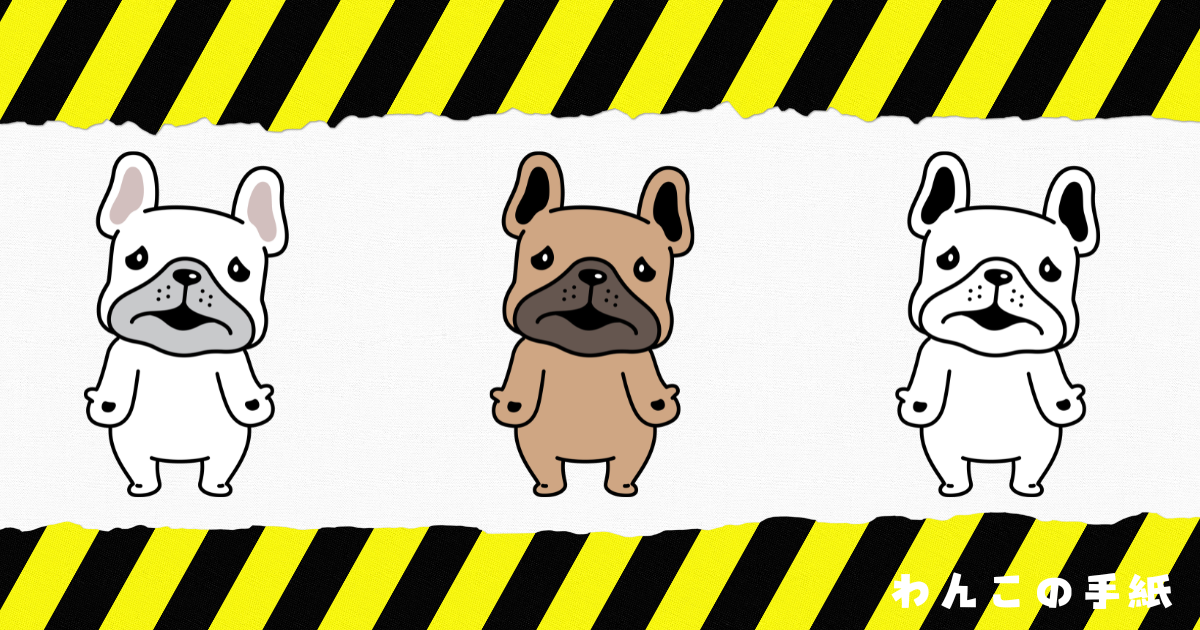
老犬の夜泣きを改善しようとする際に、飼い主の行動が逆効果になってしまうことがあります。
ここでは、夜泣きを悪化させる可能性のあるNG行動について解説します。
①夜泣きを無視し続ける
老犬が夜泣きをする原因には、不安や痛み、認知症などの可能性があります。
無視し続けると、犬は「不安が解消されない」と感じ、さらに鳴き続けることもあります。
対策
- まずは夜泣きの原因を探ることが大切。
- 健康チェックを行い、痛みがある場合は獣医師に相談する。
- 必要に応じて安心できる環境を整える。
②すぐに抱き上げる・過剰に反応する
飼い主が夜泣きをするたびにすぐに抱き上げたり、過剰に構いすぎると、犬は「鳴けば構ってもらえる」と学習してしまいます。
これが習慣化すると、夜泣きがエスカレートすることがあります。
対策
- 鳴いたらすぐに対応するのではなく、落ち着くまで様子を見る。
- どうしても鳴き止まない場合は、静かに声をかけて安心させる。
- ルールを決めて対応し、過剰な反応を避ける。
③大きな声で叱る
夜泣きが続くと、つい「うるさい!」と怒鳴ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、犬にとっては「何かよくわからないけど、飼い主が怒っている」という状況になり、不安が増すだけです。
対策
- 怒るのではなく、冷静に対応する。
- 低い声で落ち着いたトーンで「大丈夫だよ」と声をかける。
- 叱るのではなく、原因を取り除くことを優先する。
④生活リズムを崩す
夜泣きが続くと、「昼間にたくさん寝かせてあげたほうがいいのでは?」と思うかもしれません。
しかし、昼間に寝すぎると、夜になって眠れなくなり、夜泣きが悪化する可能性があります。
対策
- 昼間の活動量を増やし、適度に疲れさせる。
- 朝夕の散歩を習慣化し、体力を発散させる。
- 日光浴をさせ、体内時計を整える。
⑤夜間におやつを与える
「おやつを与えれば落ち着くかも?」と思って夜泣きのたびに食べ物を与えると、「夜泣きをすればおやつがもらえる」と学習してしまいます。
対策
- 夜泣きが始まる前に、寝る前のルーチンを整える。
- おやつではなく、優しく声をかけるなどの方法で落ち着かせる。
- どうしても何か与えたい場合は、夜泣きをしていないときに与える。
これらのNG行動を避け、適切な対応を心がけることで、老犬の夜泣きを改善しやすくなります。
飼い主のストレスを減らすための工夫
老犬の夜泣きが続くと、飼い主自身のストレスや疲労も蓄積されてしまいます。
飼い主が健康でいることは、犬のケアを続けるうえで非常に重要です。
ここでは、飼い主の負担を減らすための具体的な工夫を紹介します。
①家族やサポートを活用する
夜泣きのケアを一人で抱え込まず、家族やペットシッターなどの協力を得ることで、負担を軽減できます。
対策方法は、以下の通り。
- 家族と役割分担をする:夜間の対応を交代制にすることで、飼い主がしっかり睡眠をとれるようにする。
- ペットシッターや老犬介護施設を利用する:どうしても休みたいときは、プロのサポートを受けるのも有効。
②騒音対策を行い、睡眠の質を向上させる
老犬の夜泣きが続くと、飼い主の睡眠が妨げられることがあります。
自分の睡眠環境を工夫することで、負担を軽減できます。
対策方法は、以下の通り。
- 耳栓やホワイトノイズを活用する:音を遮断することで、飼い主の睡眠を守る。
- 別室で寝ることを検討する:夜泣きの声が気になる場合、一時的に寝室を分けるのも選択肢のひとつ。
③ストレスを発散できる時間を作る
飼い主自身がストレスを溜め込まないよう、適度にリラックスできる時間を確保しましょう。
対策方法は、以下の通り。
- 適度な運動を取り入れる:散歩や軽いストレッチなど、リフレッシュする時間を作る。
- 趣味の時間を確保する:読書や音楽など、自分の好きなことに没頭する時間を設ける。
- 気軽に相談できる環境を作る:同じ悩みを抱える飼い主と情報交換をすることで、精神的な負担が軽減されることも。
④完璧を求めすぎない
「夜泣きを絶対になくさなければ」と思いすぎると、かえってプレッシャーになり、疲れてしまいます。
対策方法は、以下の通り。
- 無理に完璧な対応をしようとしない
- 少しずつ改善していく姿勢を持つ
- 辛いときは気持ちをリセットする時間を作る
⑤老犬との時間をポジティブに捉える
夜泣きが続くと、ついイライラしてしまうこともあります。
しかし、老犬との時間は限られています。夜泣きを「最後の介護の時間」と捉えることで、気持ちが楽になることもあります。
- 「一緒に過ごせる時間を大切にしよう」と考える
- 小さな変化を楽しむ気持ちを持つ
- 老犬との思い出を増やす機会と考える
飼い主の心の余裕が、老犬にも伝わります。
無理をせず、自分のペースでケアを続けていきましょう。
夜泣き対策におすすめのグッズ

老犬の夜泣きを軽減するために、市販されているさまざまなグッズを活用することができます。
ここでは、夜泣き対策に役立つアイテムを紹介します。
①安眠サポートベッド
老犬の関節や筋肉に配慮したベッドを使用することで、寝心地が良くなり、夜泣きを軽減できることがあります。
- 低反発マットレス付きベッド:関節にかかる負担を減らし、快適な睡眠をサポート。
- 体圧分散クッション:長時間寝ていても疲れにくい設計。
- ふち付きベッド:体を囲むデザインで安心感を与える。
②リラックス効果のあるアロマグッズ
犬のリラックスを促すアロマを活用することで、不安感を和らげ、夜泣きを抑える効果が期待できます。
- ラベンダーやカモミールのアロマディフューザー:落ち着きを促し、リラックス効果を高める。
- アロマスプレー:寝床や毛布に軽く吹きかけることで、穏やかな気分に。
- フェロモン拡散器:犬が安心するフェロモンを拡散し、不安を軽減。
③ホワイトノイズマシン・リラックス音楽
夜泣きが外部の音に反応している場合、ホワイトノイズやリラックス音楽を活用することで、犬が落ち着く可能性があります。
- ホワイトノイズマシン:一定の音を流し、外部の騒音を遮断。
- 犬専用リラックス音楽:クラシック音楽や自然音を流すことで、リラックス効果を促す。
④老犬用の防音アイテム
周囲の音に敏感な犬は、外部の騒音によって夜泣きを引き起こすことがあります。
そのため、防音グッズを活用するのも効果的です。
- 厚手の防音カーテン:外部の音を遮断し、静かな環境を作る。
- 防音クッションやマット:振動や音を吸収し、落ち着いた空間を作る。
⑤ 夜間見守りカメラ
夜泣きの原因を特定するために、ペットカメラを設置すると、愛犬がどのようなタイミングで鳴いているのかを確認できます。
- スマートペットカメラ:夜間でもクリアに撮影できる赤外線機能付き。
- 遠隔操作で声をかけられるタイプ:離れた場所からでも愛犬を安心させられる。
⑥睡眠をサポートするサプリメント
睡眠を促す成分を含んだサプリメントを活用することで、老犬の夜泣きを軽減できる可能性があります。
- メラトニンサプリメント:体内時計を整え、睡眠の質を向上させる。
- カモミールエキス配合サプリ:リラックス効果があり、不安を軽減。
- オメガ3脂肪酸配合サプリ:脳の健康を維持し、認知症の進行を遅らせる。
⑦犬用おむつ・トイレグッズ
老犬は夜間にトイレの回数が増えることがあり、それが夜泣きの原因となることもあります。
トイレ環境を整えることで、夜間の不快感を軽減できます。
- 犬用おむつ:夜間のトイレの失敗を防ぎ、快適な睡眠環境を維持。
- 吸水性の高いトイレシート:排泄時の不快感を減らす。
- トイレの場所を寝床の近くに移動する:移動の負担を減らし、夜間のストレスを軽減。
これらのグッズを上手に活用し、愛犬が安心して夜を過ごせる環境を整えていきましょう。
夜泣きに関連する病気

老犬の夜泣きは、単なる習慣や環境の問題だけでなく、病気が関係していることもあります。
ここでは、夜泣きの原因となる可能性のある病気について紹介します。
① 認知症(認知機能不全症候群)
老犬に最も多く見られる夜泣きの原因のひとつが、認知症(認知機能不全症候群)です。
認知症になると、昼夜の区別がつかなくなったり、理由もなく不安を感じたりして夜泣きを引き起こすことがあります。
主な症状
- 夜中に歩き回る
- 方向感覚を失い、同じ場所をぐるぐる回る
- 突然大声で吠える
- 飼い主の指示に反応しにくくなる
対策
- 日中の刺激を増やし、適度な運動をさせる
- 寝る前にリラックスできる環境を整える
- 認知症用のサプリメントを活用する
- 獣医師に相談し、必要に応じて治療を受ける
②甲状腺機能低下症
甲状腺機能が低下すると、ホルモンバランスが乱れ、無気力になったり、逆に落ち着きがなくなったりすることがあります。
これが夜泣きの原因になることもあります。
主な症状
- 体重増加
- 被毛の脱毛や毛並みの悪化
- 寒がりになる
- 無気力または不安定な行動
対策
- 血液検査で甲状腺ホルモンの値を確認する
- 必要に応じて獣医師の指導のもとホルモン補充療法を行う
- 適度な運動を取り入れ、ストレスを軽減する
③ 心臓病(心不全)
心臓病を患っていると、夜間に呼吸が乱れたり、苦しくなったりすることで夜泣きをすることがあります。
主な症状
- 夜間に咳をする
- 呼吸が荒くなる
- 体を横にして寝るのを嫌がる
- 散歩中にすぐ疲れる
対策
- 早めに獣医師の診察を受ける
- 心臓の負担を減らすために、塩分控えめの食事を心がける
- 必要に応じて心臓の薬を処方してもらう
④腎臓病・泌尿器系のトラブル
腎臓病や膀胱炎などの泌尿器系の病気は、夜間に頻繁に排尿のために起きる原因となり、それが夜泣きにつながることがあります。
主な症状
- 夜中に何度もトイレに行きたがる
- 水を大量に飲む
- 尿の色が濃い、または血尿が見られる
- 食欲不振
対策
- 獣医師の診察を受け、適切な治療を受ける
- 尿検査や血液検査を定期的に行い、早期発見に努める
- 夜間にトイレに行ける環境を整える
⑤関節炎やヘルニアなどの痛みを伴う疾患
老犬は関節炎や椎間板ヘルニアを発症しやすく、夜間に痛みが強くなって鳴いてしまうことがあります。
主な症状
- 立ち上がるのに時間がかかる
- 階段の上り下りを嫌がる
- 触ると痛がる
- 歩行がぎこちなくなる
対策
- 関節サポートのサプリメントを活用する
- 寝床を柔らかくし、関節への負担を軽減する
- 適度なマッサージやストレッチを行う
- 獣医師に相談し、痛み止めの処方を受ける
⑥視力や聴力の低下
老犬は加齢に伴い、視力や聴力が低下することがあります。
視力が落ちると周囲の状況が分かりにくくなり、不安から夜泣きすることがあります。
主な症状
- 物にぶつかることが増える
- 突然吠えたり驚いたりする
- 飼い主の呼びかけに反応しづらくなる
対策
- 家具の配置を変えず、環境を安定させる
- 飼い主の声をかけて安心させる
- 獣医師に相談し、視力や聴力の状態をチェックする
これらの病気が原因で夜泣きをしている可能性がある場合は、自己判断せずに獣医師に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
老犬の夜泣き原因を突き止めしっかりと対策しましょう!
老犬の夜泣きは、加齢による変化や健康問題、不安や生活リズムの乱れなど、さまざまな要因によって引き起こされます。
放置すると、犬自身の健康にも悪影響を及ぼすだけでなく、飼い主のストレスや近隣トラブルにもつながる可能性があります。そのため、早めに適切な対策を講じることが重要です。
最後に夜泣きを改善するためのポイントをまとめておきます。
生活リズムを整える:日中の活動量を増やし、夜に自然と眠れるようにする。
安心できる環境を作る:静かで快適な寝床を用意し、温度や湿度を適切に管理する。
夜泣き対策グッズを活用する:リラックス効果のあるアロマやホワイトノイズ、快適なベッドなどを試す。
トレーニングやマッサージを取り入れる:安心感を与え、ストレスを軽減する。
病気の可能性を考慮する:認知症や関節炎、甲状腺機能低下症などが原因の可能性もあるため、定期的な健康チェックを行う。
夜泣きを完全になくすのは難しいかもしれませんが、適切な対応を続けることで、愛犬の負担を減らし、飼い主も穏やかな夜を過ごせるようになります。
愛犬と向き合いながら、一緒に快適な生活を目指していきましょう。