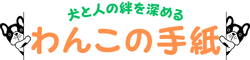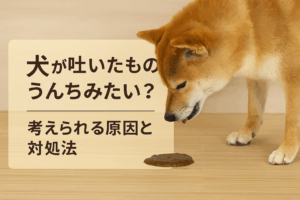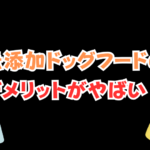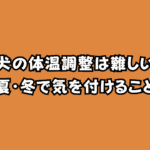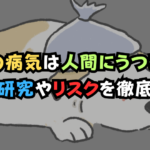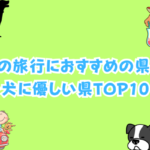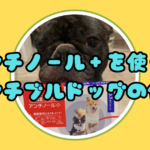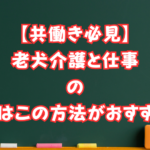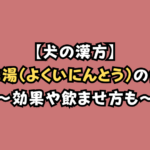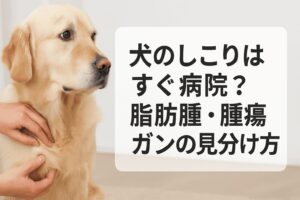保護犬を迎えることは、とても尊い決断です。
しかし、すでに先住犬がいる家庭では「仲良くしてくれるかな?」「ケンカになったらどうしよう…」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、先住犬と保護犬の関係づくりには、ちょっとしたコツと根気が必要です。
このページでは、保護犬と先住犬が自然に打ち解け、安心して暮らせる関係を築くための方法と、やってはいけないNG行動について、わかりやすく解説していきます。
初めて多頭飼いに挑戦する方も、ぜひ参考にしてください。
なぜ保護犬と先住犬は最初うまくいかないのか
保護犬と先住犬が初めから仲良くできるとは限りません。
その理由の多くは、「環境の変化に対するストレス」と「犬同士の性格や背景の違い」にあります。
まず、保護犬はこれまでにさまざまな経験をしてきています。
虐待、放棄、多頭飼育崩壊など、背景によっては人間や他の犬に対して強い不信感や恐怖心を抱えていることも。
そのため、知らない環境に連れてこられ、さらに見知らぬ先住犬と対面することは、大きなストレスになります。
一方で、先住犬にも「自分のテリトリーを守りたい」「飼い主を独占したい」といった縄張り意識や嫉妬心が生まれることがあります。
急に現れた“新入り”に対し、戸惑いや攻撃的な態度を見せるのも自然な反応です。
特に注意したいのは、年齢差や性格の違いです。
遊びたい盛りの若い犬と、落ち着いた性格の高齢犬ではテンポが合わず、ストレスを感じることも。また、最初の接し方を間違えると、お互いに「嫌な記憶」として刷り込まれてしまい、その後の関係に影響を与えてしまいます。
こうした前提を理解したうえで、関係づくりで大切なポイントについて具体的に紹介していきます。
保護犬と先住犬の関係づくりで大切な5つの基本
保護犬と先住犬が安心して暮らせる関係を築くには、最初の対応がとても重要です。
ここでは、実際に多頭飼いを成功させてきた家庭でも実践されている、5つの基本ポイントをご紹介します。
① 初対面は中立な場所で、短時間から
最初の出会いは、お互いに強い印象が残りやすいタイミングです。
いきなり室内で対面させるのではなく、公園などの「お互いにとって縄張りではない場所」で、リードをつけた状態で対面させましょう。
緊張感を避けるため、挨拶は数分程度にとどめ、様子を見ながら少しずつ時間を延ばしていきます。
② 先住犬を優先する姿勢を崩さない
飼い主の関心が新入りの保護犬に偏ると、先住犬は「自分の立場が脅かされた」と感じ、ストレスを抱えやすくなります。
ごはん、散歩、声かけの順番などは先住犬を優先することを意識しましょう。
犬にとって「自分の順位が守られている」と感じることは、心の安定につながります
③ パーソナルスペースをしっかり分ける
食事の場所や寝床、トイレなど、生活に関わるエリアは最初から分けて用意しましょう。
特に保護犬は、安心できる“自分だけの空間”が必要です。
先住犬にも「ここは自分の場所」という認識があるため、無理に共有させようとするとトラブルの原因になります。
④ 一緒に楽しい経験を積み重ねる
関係づくりに効果的なのは、「楽しい時間を一緒に過ごすこと」。
一緒に散歩へ行く、おもちゃで遊ぶ、ご褒美をあげるなど、ポジティブな体験を共有することで「相手=楽しい存在」と学習します。
ただし、無理に遊ばせようとせず、それぞれのペースを尊重するのがポイントです。
⑤ 焦らず、比べず、見守る姿勢が大事
「早く仲良くなってほしい」と思う気持ちは当然ですが、犬たちにもそれぞれのペースがあります。
仲良くなるには数週間〜数ヶ月かかることも珍しくありません。
他の家庭と比較して焦るよりも、少しずつ距離が縮まる過程を見守る気持ちが大切です。
やってはいけないNG行動5選
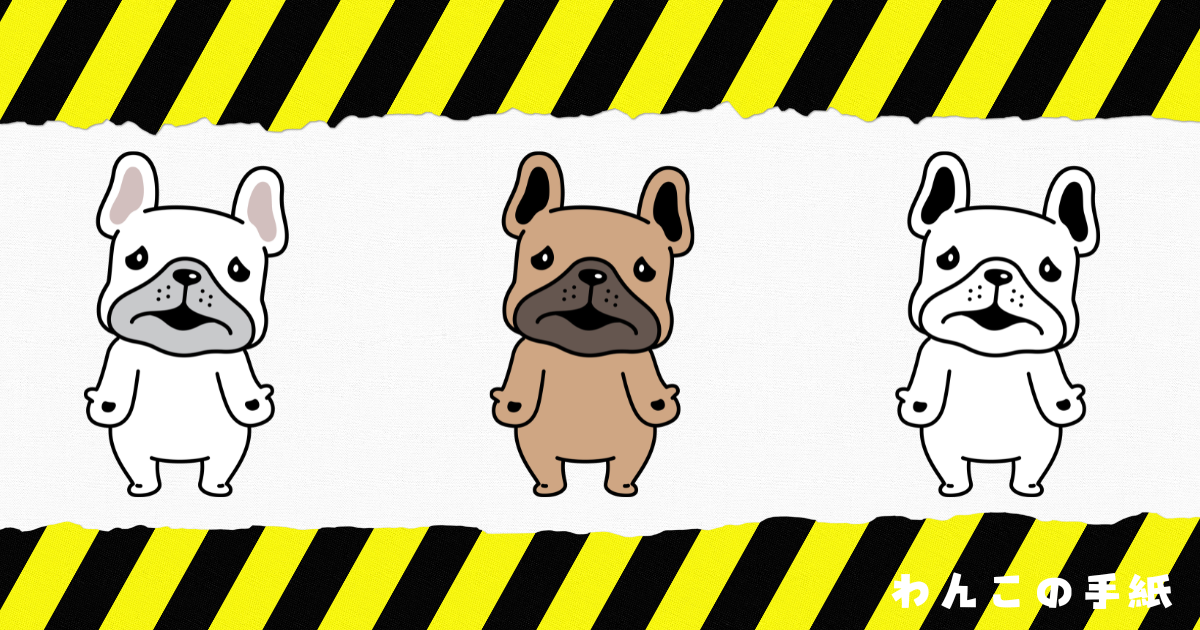
保護犬と先住犬の関係づくりでは、「良かれと思ってやったこと」が逆効果になることもあります。
以下に、よくあるNG行動を5つご紹介します。
これらを避けることで、トラブルのリスクを大きく減らせます。
① いきなり同じ部屋に長時間一緒にさせる
「すぐ仲良くなるだろう」と思って、いきなり同じ空間で自由にさせるのは危険です。
お互いに緊張している中で、逃げ場がない状況はストレスの原因に。
最初は短時間・段階的に距離を縮めることが鉄則です。
② 「どっちが上か」を人間が決めようとする
犬同士には自然と関係性(優劣や役割)が生まれます。
これを人間が無理にコントロールしようとすると、かえって混乱を招くことに。
順位づけよりも、安定した環境とルールを整えることの方が重要です。
③ 一方だけをかまいすぎる
つい保護犬に手をかけすぎたり、逆に先住犬を特別扱いしてしまったり…。
どちらかを極端に優先すると、もう一方に不満や不安が生まれます。
愛情は“平等に伝える”ことがポイントです。
④ 威嚇やケンカを感情的に叱る
犬同士のトラブルが起きたとき、大声で叱ると、飼い主との信頼関係にも傷がつく可能性があります。
叱るよりも、落ち着いて犬たちを引き離し、状況を冷静にリセットすることが大切です。
⑤ 無理に共有させる(食器・ベッドなど)
「仲良くなってほしいから」と、最初からすべてを共有させようとするのは逆効果。
食器や寝床は、安心できる“自分だけのもの”。
それを確保することで、犬たちの心も安定します。
保護犬との関係づくりをサポートする日常の工夫
先住犬との関係をスムーズに築くためには、日常生活の中でのちょっとした工夫がとても大切です。
毎日の過ごし方に少し気を配るだけで、犬たちの安心感と信頼はぐっと深まります。
一対一の時間を意識して作る
どちらの犬とも“個別に向き合う時間”を意識的に設けましょう。
保護犬には「ここは安全な場所」「自分は大切にされている」と感じさせ、先住犬には「今まで通り愛されている」と伝えることができます。
特に保護犬は、新しい環境や家族に馴染むまで時間がかかる場合もあるため、焦らず、一匹ずつと信頼関係を築くことが大切です。
落ち着いた行動にはしっかりご褒美を
犬は“自分の行動”に対して結果がついてくることで学習します。
吠えずに落ち着いていられたとき、仲良く並んで歩けたときなど、望ましい行動が見られたらすぐにほめ、ご褒美を与えましょう。
このポジティブな強化が「こうすればいいんだ」という理解を促します。
生活リズムを安定させる
犬は規則正しい生活を好みます。
毎日のごはんや散歩の時間をなるべく一定に保つことで、犬たちは「安心できる日常」を実感できます。
不安や警戒心を抱きやすい保護犬にとっては、これが特に重要です。
ふたりだけの“楽しい習慣”をつくる
例えば「夜はみんなでおやつタイム」「週末は一緒に長めの散歩」など、犬たちが楽しみにできる共通の体験を用意すると、ポジティブな感情を共有するきっかけになります。
それが信頼の土台になり、徐々に関係性が深まっていきます。
保護犬と先住犬が仲良くなるまでの体験談
ここでは、実際に保護犬と先住犬の関係づくりに取り組んだ飼い主のエピソードをご紹介します。
悩みながらも工夫を重ねて、少しずつ“家族”になっていった過程には、たくさんのヒントがあります。
保護犬の「モモ」は、元野良犬で人にも犬にも距離を置くタイプ。先住犬「ハナ」は社交的で甘えん坊だったため、迎えた当初は完全に無関心同士。ハナが近づけばモモは逃げ、モモが吠えればハナが戸惑う日々が続きました。
そこで意識したのが、「モモにもハナにもそれぞれの時間をつくること」。毎日の散歩も別々に行き、食事も寝床もきっちり分けました。そして、唯一ふたりが落ち着いていられる場所が“ベランダ”。朝の日差しを浴びながら、おやつをあげて過ごす習慣を少しずつ重ねていきました。
数ヶ月後、ある日気づいたらハナの横にモモが自然に座っていて――それが“仲良くなった瞬間”でした。今では一緒に寝たり、じゃれ合ったりする仲に。
大切なのは、「急がないこと」「比べないこと」「安心できる距離感を守ること」。
ゆっくりでも、確実に信頼は育っていきます。
まとめ|ゆっくり、でも確実に育つ信頼関係
保護犬と先住犬が仲良くなるには、環境の整備と飼い主の心がけが何より大切です。無理に距離を縮めようとせず、それぞれのペースを尊重しながら関係を築いていきましょう。
NG行動を避け、日常の中に小さな“安心”を積み重ねていけば、やがて犬同士の間に自然な信頼が生まれます。
焦らず、比べず、愛情を注ぐことが、ふたりを“本当の家族”にしてくれるはずです。